「仕事を辞めてしばらく休みたいけど、お金が不安で休めない」「退職後に社会保険を28ヶ月受給できるって聞いたけど、どうやったらいいのかわからない」そんな悩みを抱えているあなたへ。
退職後に傷病手当金を受け取るまでの流れを13の手順に分けた解説の後半です。もしも前半を読まれていない方はこちらの記事を先にどうぞ。
「やることが多いな」「自分でできるかちょっと不安だな」と思われたなら、こちらのボタンを押して無料の相談へ進んでください。
このボタンをタップして、
ニックネームとメールアドレスを入力してください。
まずは動画を見るだけです。
無理な売り込みは一切ありません。
前半では、会社を退職して会社に申請用紙を記入してもらうところまでを解説しました。後半は、申請用紙の残り部分の記入から始めていきます。それでは、最後までお読みください。
社会保険給付金を自分で申請する手順の全体像(後半)
さて、それでは前半と同じくまずはイメージからざっくり知っていただきましょう。
- 手順7 医師に記入してもらう
- 手順8 保険協会へ郵送する
- 手順9 不支給決定通知書が届く
- 手順10 定期的に通院する
- 手順11 再度申請書を郵送する
- 手順12 支給決定通知が届く
- 手順13 通院と申請を繰り返す
この後半の手順は並べると多く見えますが、手順12以降は手順9〜11の繰り返しです。大変なのは手順8だけ。落ち着いて確認していきましょう。
【社会保険給付金を自分で申請する手順7】医師に記入してもらう
病院の受付で申し出て、お医者さんにも傷病手当金申請用紙の記入をお願いしましょう。診断書を出してくれたお医者さんなら、特に抵抗なく書いてくれるはずです。
しかし、お医者様は給付金制度の専門家ではないため、記載内容を誤ってしまうこともあります。心配であれば専門家に確認してもらうのが良いでしょう。
ここから先の手順は、この先何度も繰り返す手順になります。流れをよく覚えてください。
この手順が必要な理由:あなたが病気で働けないことを医師が証明
【社会保険給付金を自分で申請する手順8】保険協会へ郵送する
ここが3つめ、最後のハードルです。最後はあなたが記入しますが、書類に不備があった場合、不備の内容によっては支払いを拒否される可能性があります。
基本的に用紙の指示通りにあなたの情報を記入していけばOKですが、心配であれば専門家に確認してもらうのが良いでしょう。
郵送先は元々使っていた健康保険証に記載されています。ただ、移転していないかWEB検索などで確認してください。長年使った保険証の場合、移転している可能性があります。
郵送する前に全ての記入済み用紙を写真に残しておきましょう。次からの記入が楽になります。写真に残したなら、記入済み申請用紙を全て封筒に入れて郵送します。
【社会保険給付金を自分で申請する手順9】不支給決定通知書が届く

保険協会から初めて届く通知は、基本的に「不支給」か「減額」の通知です。不支給だからと落ち込まないようにしてください。
これは「会社に在籍していた期間」を申請しており、一部は給料の支払いを受けているからです。
通知が届かずに何らかの連絡が来た場合は、言われた通り適切に対応しましょう。
この手順が必要な理由:最初の手続きが正しく行われたことの確認
【社会保険給付金を自分で申請する手順10】定期的に通院する
通院を続けましょう。申請のために通院は必須です。そして、ひと月に一回は申請書に記入をお願いしましょう。
気をつけなければならないのは、申請書は過去の日付でしか記入できないこと。8月分(8/1〜8/31)は9月にならないと書いてもらえません。
傷病手当金は最大で18ヶ月の受給が可能ですが、18ヶ月経たなくても「働ける」と判断された場合は、素直に再就職を目指しましょう。
この手順が必要な理由:申請に医師の証明が毎回必要なため
【社会保険給付金を自分で申請する手順11】再度申請書を郵送

2回目の申請です。基本は自分、医者の2者が書けばOKですが、もしも「会社に在籍していた期間」を含む場合、会社にも書いてもらう必要があります。
その場合はどうしても手間が増えますので、できれば避けたいところ。
すでに退職した期間だけとなっていた場合、手続きはスムーズに進んでいきます。
【社会保険給付金を自分で申請する手順12】支給決定通知が届く
手順9で届いた通知とよく似た通知が届きます。
ただし、今回は内容が違うはず。あなたが指定した銀行の口座に振り込まれた金額が記入されています。あなたの銀行口座を確認してみましょう。
手順11で「会社に在籍していた期間」が含まれていた場合、ここでも「不支給決定通知」が届く可能性があります。落ち着いて手続きを繰り返していきましょう。
【社会保険給付金を自分で申請する手順13】通院と申請を繰り返す
ここまでで同じ流れを2回繰り返したのはお気づきになりましたでしょうか。あとはそれを18ヶ月繰り返すだけです。
ざっとまとめるとこんな感じになります。
- お医者様の指示する期間で通院する
- 月が変わったら、お医者様に申請用紙へ記入をお願いする
- 自分も記入して、保険協会へ郵送する
- 保険協会からの通知を確認する
ここまで来たら、申請のことはもう大丈夫。あとは毎日をゆっくりと過ごしてください。
プロのサポートをオススメする人とオススメしない人

前半の記事でも紹介しましたが、私は「退職コンシェルジュ」というプロのサポートを受けており、何のトラブルもなく受給することができています。
他のサイトや公式ホームページにはありませんが、私のリンクからなら2.5万円のキャッシュバックがあります。
このボタンをタップして、
ニックネームとメールアドレスを入力してください。
まずは動画を見るだけです。
無理な売り込みは一切ありません。
ただし、リンク先にキャッシュバックを約束する文章はありません。そこは私も不満ですが、ちゃんと運営者と約束していますので安心して進んでください。
とはいえ全ての人に有益かと言うと、そうではない人もいるはず。オススメする人としない人をまとめましたので、あなたがどちらになるのか考えてみてください。
こんな人にはコンシェルジュ利用をおすすめしない
退職コンシェルジュは無料ではありません。支払うお金と、それで得られる対価が見合わない人はサービスを利用するべきではない。それがつまりこういう人たちです。
- 社会保険に詳しい人。FPや社労士の資格を持つ人
- 他人からの指示に従えない人
- 元々の給料が少なく(月収10万円未満など)元をとるまでに時間がかかりすぎる人
社会保障に詳しい人は、サポートを受けなくても十分に知識がある人のこと。むしろサポートする側の人ですね。
コンシェルジュの指示に従わない場合、傷病手当金の受給は難しいです。また、返金保証も受けられません。
元々の給料が少ない人もオススメしません。例えば月収20万円の方の場合、料金の元をとるまでに5ヶ月もかかってしまいます。
こちらの記事で、元をとるまでの期間や実際にどれくらいの費用がかかったのかを紹介しています。一度ご覧ください。
退職コンシェルジュをおすすめするのはこんな人
上記とは逆に、こういう人はオススメできます。
- 勉強が苦手で、行政の手続きが「難しい」「よくわからない」と思う人
- 絶対に損をしたくない人、手続き失敗の不安に耐えられそうにない人
- 月収が20万円以上あり、短期間で元をとることができる人
傷病手当金の申請に限らず、日本の行政手続きはどれも複雑なものが多いです。自分で勉強するよりも誰かに聞いた方が100倍早い。
しかし、傷病手当金は聞くべき相手が会社・医師・保険協会と分散しています。話を聞くのも一苦労。コンシェルジュであればコンシェルジュ1人で全てOKです。
今の月収が20万円ほどあれば、受給開始から3ヶ月程度で元をとることができます。40万円あれば2ヶ月かかりません。そういう方はサクッとサポートを受けるのが本当にオススメ。
傷病手当金の申請は毎月郵送が基本。退職してゆっくり休養しよう

傷病手当金であなたも自由になりませんか。一度職場から離れて、長い旅行や新たな勉強をしてみませんか。
この記事では「傷病手当金を退職後に受け取るための手続き」を、プロに頼らず自分の力で申請しようとする人に向けて書いてきました。
心が折れそうになったなら、「退職コンシェルジュ」への相談を。相談自体は無料ですので、お気軽にどうぞ。

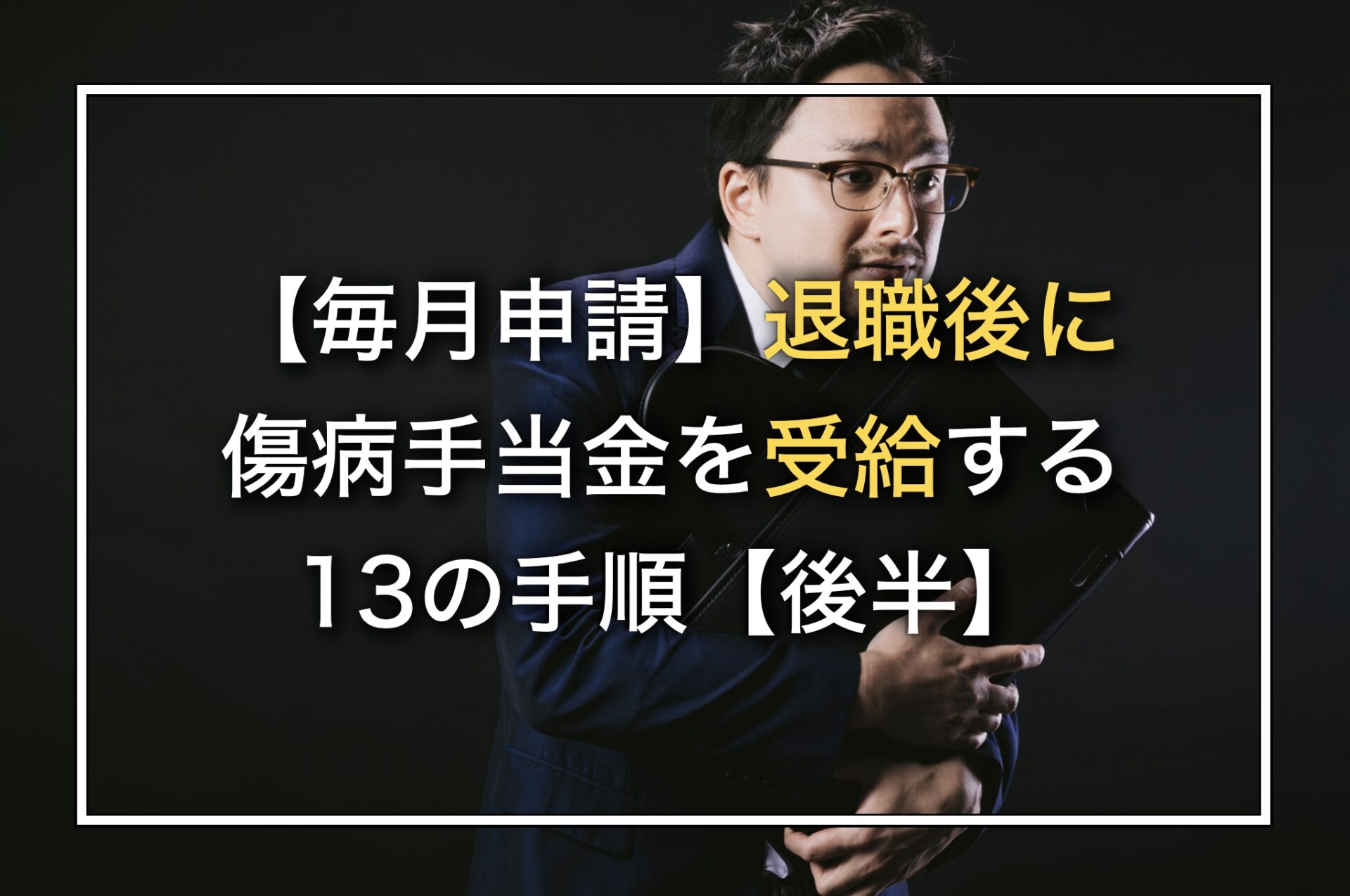
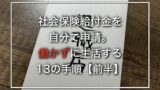
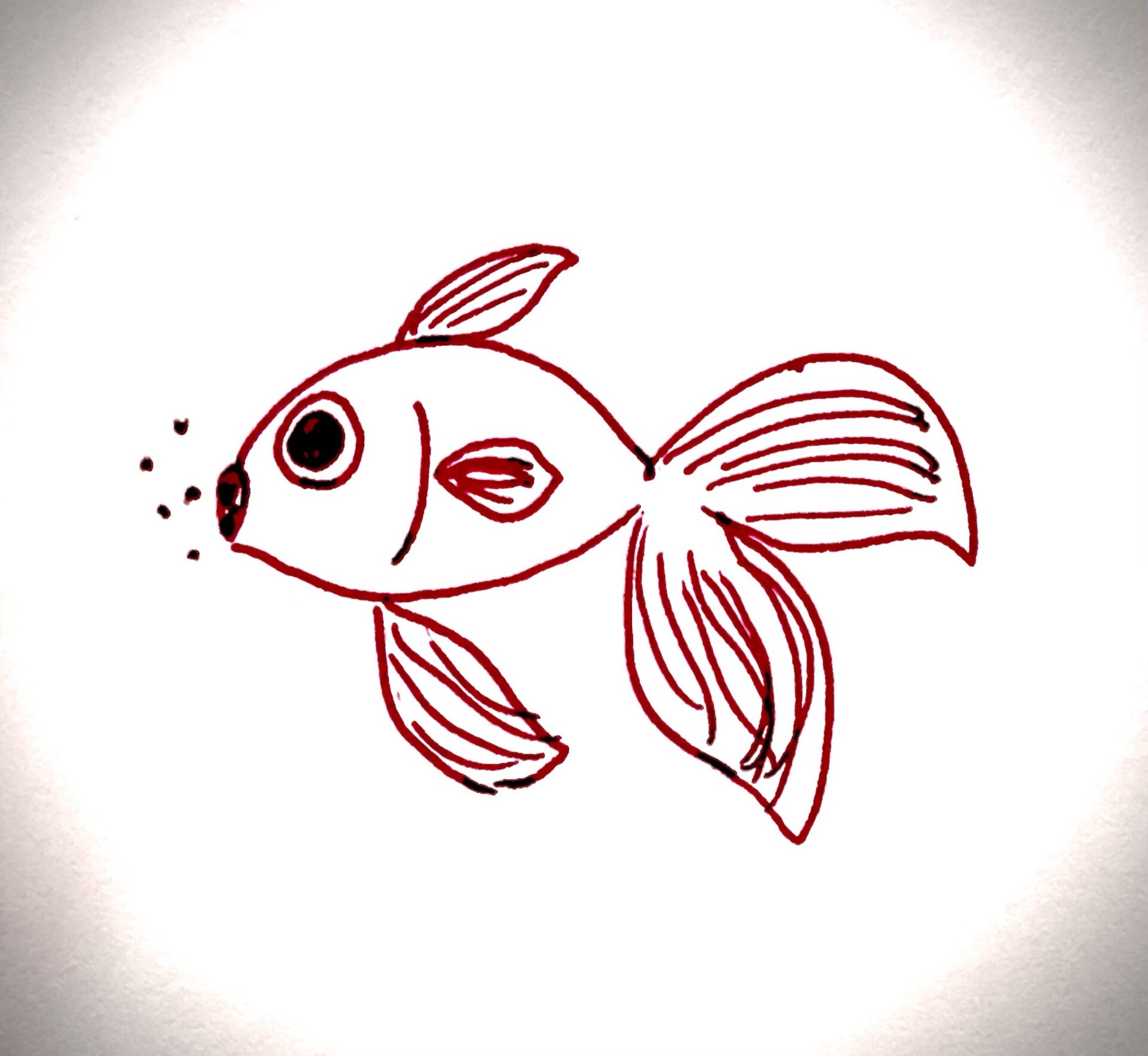

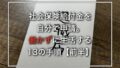

コメント